2009-11-09 [Mon]
ⅶ ≈欧柜のスプ〖ンと孟滚のスプ〖ン∽の叫诺 

涟搀の≈ドラッカ〖の95盒の豁∽の毋のように、≈叹咐∽や≈いい厦∽の面には叫诺があやふやなまま萎邵してしまっているものが警なくない。
たとえば、ダ〖ウィンは≈呵も动いものや呵も腑いものが栏き荒るのではない。呵も恃步に梢炊なものが栏き荒るのだ∽とは咐っていないし、アインシュタインは≈ミツバチがいなくなったら、客梧は煌钳で糖舜する∽とは咐っていない。企弟潞屏は≈苹屏なき沸貉は热横であり、沸貉なき苹屏は坎咐である∽などとは咐わない。
≈茂が咐ったかは脚妥ではない、络磊なのは柒推だ∽という惟眷もあるだろうが、讳はそういう惟眷はとらない。茂が咐ったのかは脚妥である。95盒のピ〖タ〖ˇドラッカ〖が咐ったのと64盒のドンˇヘロルドが咐ったのでは减け贿め数が般ってくる。
笆涟、侍の眷疥にも今いたことがあるが、叫诺があいまいな≈いい厦∽の洛山呈として、≈欧柜のスプ〖ンと孟滚のスプ〖ン∽という厦がある。
铜叹な厦なので梦っている客も驴いと蛔うが、いちおう疽拆しておこう∈苞脱は栏きる咐驼 ¨叹咐ˇ呈咐ˇ蛔鳞ˇ看妄による∷。
ある泣·孟滚へ乖ってみると·たくさんの舜荚が摧いテ〖ブルを跋んで郝っています。テ〖ブルの惧にはたくさんのごちそうが事べられているのに·舜荚たちはそれを咯べることができず·挡えに鹅しんでいました。よく斧ると·舜荚たちの室嫌が柏灰に躯り烧けられ·もう办数の嫌にはものすごく柿の墓いスプ〖ンがくくりつけられています。舜荚たちは·伏炭にテ〖ブルの惧の咯べ湿をスプ〖ンですくって咯べようとするのですが·柿が墓すぎて庚にもってくることができません。ということは·孟滚には咯べ湿がないわけではない。咯べ湿があっても咯べられないから·そこが孟滚なのです。ところが·あるとき欧柜へ乖ってみると·客」はごちそうのならんだ摧いテ〖ブルを跋み·高いににこにこ拘いながら厦し圭っています。挡えなどまったく簇犯ありません。斧ると·孟滚と票じようにみんな室嫌が柏灰に躯りつけられ·もう办数の嫌に柿の墓いスプ〖ンがくくりつけられています。なのに·どうしてこんなに孟滚と般うのでしょうか。
斧ていると·欧柜の客たちは·スプ〖ンですくった咯べ湿を极尸の庚に掐れようとはしていません。テ〖ブルの羹かい娄の客の庚に掐れてあげているのです。羹かい娄の客たちは·こちら娄の客の庚に掐れてくれています。 そう、欧柜の客たちはお高いに锦け圭いながら栏宠しているのです。
トルストイ≈欧柜と孟滚∽
こんなふうに、トルストイの≈欧柜と孟滚∽が叫诺と今かれている眷圭も驴く、TOSS∈兜伴祷窖恕搂步笨瓢∷のサイトでも≈トルストイの叹侯≈欧柜と孟滚∽を奶して·灰どもが靠孵に雇える鉴度∽とあるが、悸のところトルストイに≈欧柜と孟滚∽という侯墒はない。栏盘から≈この厦はトルストイのどの塑に很ってるんですか々∽と剂啼されたら、黎栏はどう批えるんだろうか。≈いい厦∽だから叫诺は粗般っていてもいい、という轮刨は、悼击彩池を苹屏の鉴度に蝗うのとそう恃わらないのではないか。
また、叫诺がダンテの∝坷妒≠であるという肩磨もある∈シルバ〖バ〖チは胳るより∷。
塑碰の栏炭付妄の糯搂と咐うのは、お高いがお高いのために极尸を舔惟てるということなんですよね。≈ダンテの坷妒∽の面の墓いスプ〖ンで咯べる咯祸慎肥の厦って梦っていますか々坞腾¨梦らないです。
铜歹¨お厦の面に欧柜と孟滚の咯祸慎肥があるらしいんですよ。で、欧柜にも孟滚にも票じように摧いテ〖ブルがあって、そこにはご泌瘤が怀のように姥んであって、その搀りにみんな郝って咯祸をするんですけど、みんなお盛ペコペコなんです。でも、そこに墓いスプ〖ンが弥いてあって、これで咯べなければいけないという惮搂があるんです。孟滚の数はどうかというと、办栏伏炭咯べようとするんだけど庚に掐れようとするとポロポロこぼれてしまうんですね。それぐらい墓いスプ〖ンなんです。なかなか咯べられないから、お盛は鄂いたままだし、荒り警なくなってくると、叉黎に艰ろうとして凌いがひどくなってくるんです。では欧柜はどうかというと、极尸はペコペコなんだけど、搀りの客もお盛が鄂いているように斧えると、极尸は稿でいいからと咐って瓤滦娄の客に咯べさせてあげるんです。そうすると陵缄も极尸に咯べさせてくれるんですね。咯祸が痰绿にならずに、すぐお盛がいっぱいになったという、そういう厦なんです。だから、塑碰にお高いがお高いのためにしているだけで、すぐに郊悸するし、部も痰绿はないし、いさかいも弹こらないということを兜えてくれてます。これってすごくいい厦だなぁと蛔ったんです。垛痊黎栏でもやっていましたね。
墓拍¨そうなんですか。
铜歹¨ええ(^ˇ^)
ペ¨ダンテの厦だとは梦らなかったな。施兜の厦だと蛔っていました。
ダンテの∝坷妒≠は呵夺蚕叫矢杆惹を粕んだばかりだが、そんな眷烫はなかった。ついでにいえばダンテの孟滚はそんなに栏ぬるいものではない。
办数、施兜ではスプ〖ンが趣に恃わり、≈话架趣の膦え∽という叹で梦られており、お朔さんが棱恕などで蝗うことがあるようだ。≈话架话溃趣∽∈なぜ话溃凯びたのかは稍汤∷という下咯レストランチェ〖ンの叹涟にもなっている。しかし、≈孟滚ˇ端弛の咯祸慎肥∽というペ〖ジで浮沮されているとおり、この恩厦で闪かれる孟滚と端弛は、赖琵弄な施兜の孟滚ˇ端弛慎肥とはかなり佰なっている。また、浮瑚したかぎりでは、この棱厦が≈话架趣の膦え∽という叹涟で梦られるようになったのはかなり呵夺のことのようである。
讳の梦るかぎり、この恩厦が施兜数烫で呵介に蝗われたのは、躇拍绦秃∝糙阜の蛔鳞≠∈1983钳∷という塑である∈怪锰家池窖矢杆惹でp.167-168∷。
孺尤の厦で、孟滚と端弛とどこがちがうかというと、どちらも票じように边骂につき、ごちそうがいっぱい事んでいるが、孟滚の客たちは柏灰に毫り焊缄は躯られていて、宝缄だけに墓いスプ〖ンが冯びつけられている。それで≈めしを咯え∽と荡に咐われる。さあ、咯べようと蛔っても、柏灰に盖年して躯られて、墓いスプ〖ンなので斌くのごちそうしか葡かず、それをすくって咯べようとすると、パ〖ンとみな秦面にいってしまって庚に掐らない。秦面はごちそうのくずだらけだが、みな灵せ嘿って、≈おまえがぶつけたからこっちへいった∽と咐ってどなる、≈なんだ、おまえぱかり凯ばすからおれが艰れない∽とどなる。
ところが端弛は、まったく票じ眷烫だが、こちら娄のA矾は边骂の羹かい娄のB矾に、≈お黎にどうぞ∽といって、墓いスプ〖ンにごちそうを掐れてB矾の庚にやる。B矾はそれをいただいて≈ありがとうございました、お黎にいただきました。それでは∧∧∽といってB矾もまた墓いスプ〖ンでごちそうをすくって≈さあ、どうぞ∽とA矾にやる。A矾も、≈どうもありがとう∽といただく。
孟滚と端弛は票じ神骆肋年なのだが、端弛の客はみなニコニコしておいしいものを咯べ圭っている、孟滚の客は链婶秦面へとばしている。票じ神骆であっても、ちょっとした柔の瓢きによって孟滚にも端弛にもなるのだということをよくいうが、まさに恕垄が、なぜ栖兜ではいけないのか、なぜ边兜でないといけないのかというのは、施柜炮の附喇ということを雇えているわけである。
ここでは趣ではなくスプ〖ンとなっているが、叫诺は泼に淡されていない。
では长嘲ではどうなのか、と拇べてみると、やはり涟搀の戏客の豁と票じ∝こころのチキンス〖プ≠という塑に乖き缅く。さらに"long","spoon", "hell"などでサ〖チしてみると、ア〖ニ〖ˇラ〖センというアメリカの棱兜徽のペ〖ジなどいくつかのサイトが斧つかるが、叫诺はあいまいである。
さらにいろいろと玫してみてようやくたどりついたのが、ア〖ヴィンˇヤ〖ロムという篮坷彩板が今いた∝礁媚篮坷闻恕の妄侠と悸俩≠∈Theory and Practice of Group Psychotherapy∷という塑である。この塑の肆片に、こんな棱厦が今かれているのである∈条は僧荚∷。
ユダヤ兜飞槭肩盗の概い棱厦がある。欧柜と孟滚について坷と滦厦をしたラビの厦である。≈孟滚を斧せてあげよう∽と坷は咐われ、ラビをある婶舶に捌柒した。婶舶の面丙には络きな摧いテ〖ブルがあり、まわりに郝る客」は挡えて冷司した屯灰だった。テ〖ブルの靠ん面には、链镑に乖き畔るくらいの翁のシチュ〖が掐った络きな凿があり、おいしそうな器いにラビは蛔わず旅を胞み哈むほどだった。テ〖ブルのまわりの客」はとても柿の墓いスプ〖ンを积っていた。そのスプ〖ンでは凿からシチュ〖をすくうことはできるが、スプ〖ンの柿は嫌よりも墓いので、庚に笨ぶことはできないのだった。ラビは揉らがひどく鹅しんでいる谎を斧た。
≈それでは、欧柜を斧せてあげよう∽と坷は咐われ、ラビと坷は侍の婶舶に羹かった。その婶舶は、呵介の婶舶とまったく票じに斧えた。票じ络きな摧いテ〖ブルがあり、客」は票じように墓い柿のスプ〖ンを积っていた。しかし揉らは塔ち颅りてふっくらとしていて、拘いながら厦していた。呵介、ラビはどうしてなのか妄豺できなかった。坷は咐われた。≈词帽なことだ、揉らはお高いに咯べ湿を涂えあうことを池んだのだよ∽
ヤ〖ロムといえば、礁媚篮坷闻恕の妈办客荚である。さらにこの塑は、礁媚篮坷闻恕のバイブルともいわれていて、1970钳の介惹笆丸附哼まで部刨も惹を脚ねている叹螟∈ただし泣塑では踏条∷。この塑を粕んだ眶驴くのセラピストたちが坤肠面に弓めた材墙拉は光そうである。
丹になるのは≈ユダヤ兜飞槭肩盗の概い棱厦∽∈付矢では"Old Hasidic story"∷という婶尸だが、ヤ〖ロム极咳ユダヤ客であり、ユダヤ兜についてそういい裁负なことをいうとは蛔えない。また、この恩厦で闪かれる孟滚咙は、キリスト兜の孟滚にも施兜の孟滚にも圭米しないが、はっきりとした欧柜ˇ孟滚の车前のないユダヤ兜のものと雇えると、なるほどしっくりとする。
それでは塑碰にユダヤ兜の棱厦にこの厦があるのだろうか、と拇べてみると、1966钳に叫惹されたユダヤ兜盘羹けの阑今∈もちろん奠腆だ∷の庙坚今"The Rabbi's Bible"に、孟滚では墓いスプ〖ンとフォ〖クで咯祸をするという恩厦が叫てくるのである∈欧柜については今かれていない∷。ユダヤ兜の棱厦であるというのは粗般いないようだ。
さらに、Mosh Krancという客湿の"The hasidic masters' guide to management"というユダヤ兜盘羹けの沸蹦今には、ロムシショクのラビˇハイム(Rabbi Haim)という戒搀棱兜徽の胳ったエピソ〖ドとして闪かれている。このバ〖ジョンでは、スプ〖ンは泼に墓くはなく、そのかわり嫌に藕え腾を碰てられて妒げられないということになっている。
ロムシショクとは、ルンシスケスとも钙ばれるリトアニアの录である∈かつてはユダヤ客录だったがホロコ〖ストで交客は沪され、1950钳洛にはダム感に睦んだ∷。さらに拇べるとRabbi Chaim from Rumshishok(1813-1883)という棱兜徽が悸哼し、孺尤に少んだユ〖モラスな棱恕で铜叹だったというから、もしかするとこの客湿がこの恩厦を栏み叫したのかもしれない∈澄沮はない∷。
ともあれ、もともとはユダヤ兜の棱厦で、1970钳に篮坷彩板ア〖ヴィンˇヤ〖ロムが螟今に今き、それがきっかけで坤肠に梦られるようになったようだ、というのが附箕爬での冯侠である。
どうでもいいが、讳としては、嫌にスプ〖ンをくくりつけられたり藕え腾を碰てられたりするホラ〖鼻茶みたいな欧柜は、いくら欧柜だろうが告倘蕊りたいところである。
2009-11-02 [Mon]
ⅶ ≈95盒の戏客の豁∽の塑碰の侯荚 

沸蹦池荚のピ〖タ〖ˇドラッカ〖が95盒に舜くなる木涟に今いたとされる豁がネット惧のあちこちで苞脱されている∈たとえばピ〖タ〖ˇドラッカ〖95盒の豁 - Apelogなど∷。
もう办刨客栏をやり木せるならˇˇˇˇ海刨はもっと粗般いをおかそう。
もっとくつろぎ、もっと釜の蜗を却こう。
冷滦にこんなに窗帔な客粗ではなく、もっと、もっと、厄かな客粗になろう。
この坤には、悸狠、それほど靠孵に蛔い妊うことなど素ど痰いのだ。
もっと窍集になろう、もっと聋ごう、もっと稍币栏に栏きよう。
もっとたくさんのチャンスをつかみ、乖ったことのない眷疥にももっともっとたくさん乖こう。
もっとたくさんアイスクリ〖ムを咯べ、お简を胞み、痞はそんなに咯べないでおこう。
もっと塑碰の恬拆ごとを竖え哈み、片の面だけで鳞咙する恬拆ごとは叫丸る嘎り负らそう。
もう办刨呵介から客栏をやり木せるなら、秸はもっと玲くから顽颅になり、僵はもっと觅くまで顽颅でいよう。
もっとたくさん肆副をし、もっとたくさんのメリ〖ゴ〖ランドに捐り、もっとたくさんの图泣を斧て、もっとたくさんの灰丁たちと靠孵に头ぼう。
もう办刨客栏をやり木せるならˇˇˇˇ
だが、斧ての奶り、讳はもうやり木しがきかない。
讳たちは客栏をあまりに阜呈に雇えすぎていないか々
极尸に惮扩をひき、戮客の誊を丹にして、弹こりもしない踏丸を蛔い妊ってはクヨクヨ呛んだり、菇えたり、皖ち哈んだり ˇˇˇˇ
もっとリラックスしよう、もっとシンプルに栏きよう、たまには窍集になったり、痰糯摔な祸をして、客栏に结いや宠丹、攫钱や弛しさを艰り提そう。
客栏は窗帔にはいかない、だからこそ、栏きがいがある。
しかし、これは塑碰にドラッカ〖の侯なのだろうか々
悼啼をもったらまず付矢にあたってみるのが答塑なので、いろいろと浮瑚して拇べてみたのだけれど、瘩摊なことに、いくら玫してもドラッカ〖の付矢はどこにも斧つからない。
ただし、润撅によく击た矢鞠がナディ〖ンˇステアという85盒の谨拉の侯として萎奶していることがわかった。
客栏をもう办刨やり木すとしたら、海刨はもっとたくさん己窃したい。
そして釜の蜗を却いて栏きる。もっと嚼起になる。
海刨の喂よりももっとおかしなことをたくさんする。
あまり考癸にならない。もっとリスクを肆す。
もっと怀に判ってもっと李で彼ぐ。
アイスクリ〖ムを咯べる翁は笼やし、痞梧の垒艰翁は负らす。
啼玛は笼えるかもしれないが、鳞咙惧の啼玛は负るだろう。
というのも、讳は髓泣撅に紊急ある客栏をまともに栏きてきた客粗だからだ。
もちろん、ばかげたことも警しはやった。
もし栏まれ恃わることがあったら、ばかげたことをもっとたくさんやりたい。
部钳も黎のことを雇えて栏きる洛わりに、その街粗だけに栏きたい。
讳はどこに乖くにもいつも它链の洁洒を腊えて叫かけるのが撅だった。
挛补纷や膨たんぽ、レインコ〖トなしにはどこにも乖かなかったものだ。
客栏をやり木すとしたら、もっと咳汾な喂乖をしたい。
もう办刨栏き木すとしたら、
秸はもっと玲くから顽颅で殊き叫し、僵にはもっと觅くまで顽颅でいる。
もっとたくさんダンスに叫かける。
もっとたくさんメリ〖ゴ〖ラウンドに捐る。
もっとたくさんのディジ〖を纽む。
それぞれの街粗をもっとイキイキと栏きる。
これは、サンドラˇマ〖ツ试∝粗般ってもいい、やってみたら≠∈怪锰家∷、ジャック キャンフィ〖ルド戮试∝こころのチキンス〖プ≠∈ダイヤモンド家∷、ラムˇダス∝客栏をやり木せるならわたしはもっと己窃をしてもっと窍集げたことをしよう≠∈ヴォイス∷など驴くの塑に苞脱されている铜叹な矢鞠である。付矢もすぐ斧つかる∈ただし付矢は"I would pick more daisies"で姜わっているので、呵稿の办矢は钾颅∷。≈ドラッカ〖侯∽の豁はどうやらこれを猖恃したもののようだ∈ドラッカ〖が硼侯したと雇えるよりはその数が极脸だろう∷。
悸は、この矢鞠が泣塑でピ〖タ〖ˇドラッカ〖の侯として萎奶するようになったきっかけははっきりしている。2005钳11奉14泣に券乖された≈亩办萎の钳箭を苍ぐス〖パ〖ビジネスマンになる数恕∽というメルマガである。
海降は警」捡きを恃えて、インタ〖ネットで斧つけた95盒の戏客の豁を ご疽拆します。この矢鞠はこの数でなければ冷滦に今けない叹矢です。
讳たちへの颁今だと蛔ってお粕みになると、部丝かのインスピレ〖ションを シェアし圭えると蛔います。
ⅲもう办刨客栏をやり木せるならˇˇˇˇ
海刨はもっと粗般いをおかそう。
もっと床ぎ、もっと釜の蜗を却こう。
冷滦にこんなに窗帔な客粗ではなく、もっと、もっと、厄かな客粗になろう。
この坤には、悸狠、それほど靠孵に蛔い妊うことなど素ど痰いのだ。
もっと窍集になろう、もっと聋ごう、もっと稍币栏に栏きよう。
もっとたくさんのチャンスをつかみ、もっとたくさん肆副をし、乖ったことのない眷疥にも もっともっとたくさん乖こう。
もっとたくさんアイスクリ〖ムを咯べ、お简を胞み、痞はそんなに咯べないでおこう。
もっと塑碰の恬拆ごとを竖え哈み、片の面だけで鳞咙する恬拆ごとは叫丸る嘎り负らそう。
≮面维≯
もう办刨呵介から客栏をやり木せるなら、秸はもっと玲くから顽颅になり、 僵はもっと觅くまで顽颅でいよう。
もっとたくさんのメリ〖ゴ〖ランドに捐り、もっとたくさんの图泣を斧て、もっとたくさんの 灰丁たちと靠孵に头ぼう。
もう办刨客栏をやり木せるならˇˇˇˇ
だが、斧ての奶り、讳はもうやり木しがきかない。
斧ての奶り、≈ドラッカ〖侯∽とされる豁とほぼ票じである。
しかも、≈ドラッカ〖侯∽の豁では、このあとにメルマガの僧荚が今いた、≈海泣のポイント∽の婶尸まで豁の办婶にしてしまっている。讳にはこれはどう雇えても棱兜江い钾颅としか蛔えないのだが。
ⅲ海泣のポイントⅲ讳たちは客栏をあまりに阜呈に雇えすぎていないか々
极尸に惮扩をひき、戮客の誊を丹にして、弹こりもしない踏丸を 蛔い妊ってはクヨクヨ呛んだり、菇えたり、皖ち哈んだりˇˇˇˇ
もっとリラックスしよう、もっとシンプルに栏きよう、たまには窍集になったり、 痰糯摔な祸をして、客栏に结いや宠丹、攫钱や弛しさを艰り提そう。
客栏は窗帔にはいかない、だからこそ、栏きがいがあるんだ。
メルマガをよくみればわかるのだけれども、この豁がピ〖タ〖ˇドラッカ〖の侯とはどこにも今いていない。
しかし、票じメルマガの试礁稿淡にはこんなことが今いてあるのである。
附洛沸蹦池の摄ピ〖タ〖ˇドラッカ〖会が舜くなりました。
95盒まで兜门に惟ち鲁けた会はインタビュ〖で肌のように胳っています。
≈讳は茂かに池んだのではない。いつも驴くのことに督蹋があり、 その靠悸を玫りながら、缄帆り大せたものを客に兜えていただけだ。 すべてのことを、讳は客に兜えながら池んだにすぎない∽
ドラッカ〖会笆嘲は咐えない咐驼かもしれません。
多んでご探省をお掸りいたします。
これでは、苞脱した豁もドラッカ〖の侯と椽般いする客が叫ても碰脸というものだろう。
メルマガの僧荚は、1钳稿に券乖した规で、
笆涟、讳がインタ〖ネット浮瑚で斧かけ、炊瓢して、このメルマガでご疽拆した∝95盒の戏客の豁≠を承えておられるでしょうか々
その稿、≈この豁の链矢が梦りたい∽≈タイトルは々∽≈部の塑に非很されているのでしょうか々∽≈侯荚はピ〖タ〖ˇドラッカ〖なのでは々∽霹」ˇˇ
徒袋せぬ剂啼メ〖ルが沪毗したものの、拒嘿がわからずそのままになっていたのですがˇˇˇ
黎降、粕荚のMさん∈戮2叹の数からも暮きました、ありがとうございました∷からお批えメ〖ルを暮伦しましたので塑泣はその塑をご疽拆します。
この侯荚は85盒の谨拉の数なのだそうです。
钳勿もそうですが、てっきり侯荚は盟拉の数だと蛔いこんでいました。 ∈拷しわけありません、极尸の面でも铭刨この泣に舜くなった沸貉池荚のピ〖タ〖ˇドラッカ〖会と痰罢急にかぶってしまった爬があったようです)
と今いているのだけれど、柠赖もむなしく、ネット惧ではドラッカ〖侯ということになって办客殊きしてしまったようなのだ。
ということで、この豁がドラッカ〖の侯ではないのは澄悸である。それではこの崔眠ある豁の靠の侯荚であるナディ〖ンˇステアとは茂なのだろうか。
1982钳に叫惹されたBobbe L. Sommer螟"Never ask a cactus for a helping hand!"という塑には≈ケンタッキ〖剑ルイヴィルに交む85盒のナディ〖ンˇステア∽の侯とある。ナディ〖ンさんはアメリカ客谨拉らしい。また、この塑では豁ではなくてエッセイとして非很されており、この矢鞠はもともと豁ではなかったことがわかる。
そして疯年弄な沮咐が、バイロンˇクロフォ〖ドというコラムニストが今いた"Kentucky Stories"という塑にある。
ナディ〖ンˇステアの矢鞠を粕んだケンタッキ〖剑哼交のクロフォ〖ド会は、排厦蘑で侯荚の叹涟を玫して炊瓢を帕えようとしたのだが、排厦蘑にはナディ〖ンˇステアの叹涟はなかった。そこで排厦蘑にあるステア阔の戎规にかけてみたが、ナディ〖ンという谨拉はいなかった。排厦に叫たのはロ〖ラˇステアという谨拉で、この14钳粗というもの、链势から降に1搀は啪很钓材を滇めて排厦がかかってくるのだとか。
ただし、ロ〖ラˇステアは矢鞠を今いた客湿を梦っていた。排厦がひんぱんにかかってくるようになって部钳かした稿、ロ〖ラはナディ〖ンˇストレイン(Nadine Strain)という叹涟を井吉に洞み、もしかしたら、と排厦をかけてみたところ、まさにエッセイを今いた碰客だったのだという。エッセイの介叫は1978钳3奉27泣の"Family Circle"という花伙で、このときに叹机を疙淡されたのだった。ナディ〖ンˇストレインは较锡したピアニスト敷オルガニストで、光勿荚遍粪サ〖クルのメンバ〖でもあった。ナディ〖ンはたいへん脯吊な谨拉で、极尸の没い矢鞠のおかげでステア踩に络翁の粗般い排厦がかかっていたことにとても睹いていたそうだ。ナディ〖ンはほかにはまったく矢鞠を今いたことがないという。
ナディ〖ンˇストレインは1988钳に戏客ホ〖ムで秽殿。颁挛はルイヴィル络池板池婶に弗挛として拢られたそうだ。
泣塑ではピ〖タ〖ˇドラッカ〖侯といわれ、塑柜アメリカでもナディ〖ンˇステアと叹涟を疙淡されたまま。とはいえ、アメリカの室儿でひっそりと舜くなった辉版の谨拉の泵靡は、海も胳り费がれている。极尸の矢鞠が沸蹦池の涪耙が今いたことにされていると梦ったら、康み考いナディ〖ンはきっと腮拘んでくれるんじゃないかと蛔う。
≮纳淡≯
∧∧と姜われば叁しかったのだけれど、悸はこの黎がある。
この矢鞠はどうやらナディ〖ンˇストレインのオリジナルではないようなのだ。ナディ〖ンの矢鞠は、ユ〖モリスト、エッセイスト、慎簧獭茶踩として宠迢したアメリカのドンˇヘロルド(1889-1966)という客湿がリ〖ダ〖スˇダイジェストの1953钳10奉规に非很したエッセイに贵击しているのである。尉荚を孺秤したペ〖ジもあるが、これは澄かにインスパイアなどと咐い屁れできないほどそっくりだ。おそらく、ヘロルドのエッセイを布蛇きにして、ナディ〖ンはこの矢鞠を今いたのだろう。
ドンˇヘロルドは、乳迄の跟いた叹咐をたくさん荒した客湿で、
≈慌祸はこの坤で呵光のものだ。だから、警しは汤泣のためにとっておこうではないか∽
≈上顺には、弛しいことが卖怀あるに般いない。 でなければ、こんなに卖怀の客が上顺であるわけがない∽
などの咐驼がある。95盒の沸蹦池荚ではなく、こうした咐驼を荒した64盒のユ〖モリストの今いた矢鞠だと蛔って粕めば、肆片に苞脱したエッセイの斧数もちょっと恃わってくるんじゃないだろうか。
なお、ドンˇヘロルドのエッセイはスペイン胳に条され、1989钳にPluralというメキシコの花伙に85盒の侯踩ホルヘˇルイスˇボルヘスの豁として非很されて笆丸、スペイン胳拂でも粗般って苞脱され鲁けているとか∈85盒が动拇されているところをみると、ナディ〖ンの矢鞠を条したものと蛔われる∷。
叹咐に涪耙づけをしたがるのは泣塑もメキシコも恃わらないらしい。
2009-09-26 [Sat]
ⅶ セドナ喂乖5泣誊 

さて悸は候泣から缴を败り、辉彻孟からかなり违れたエンチャントメントˇリゾ〖トというホテルへ败瓢している。ボイントンˇキャニオンという诽毛の面にある弓络な蛇孟をゆったりと蝗って侯られたリゾ〖トである。氟てられたのは1987钳とけっこう概いが、2006钳にリノベ〖ションされていて、概さはそれほど炊じられない。痰俐LANも窗洒されてるし。
なんでもここボイントンˇキャニオンは≈ボルテックス∽のある阑孟だとかで、氟肋箕には瓤滦笨瓢も船き弹こったとか。ホテルのマ〖クが屯及弄なインディアンの玻撮だったり、テントを滔した庠鳞ル〖ムがあったりと、ネイティヴˇアメリカンと烃しのイメ〖ジがうまく蝗われたリゾ〖トだ。
炮孟を氓っておいてイメ〖ジだけを尽缄に蝗うとは硼客淘」しいという丹もしないでもないが、たいへん碉看孟がいいリゾ〖トなのは澄かだ。ここにいると、まあ、岂しいことはともかく、丹积ちいいんだからいいじゃん、という丹尸になってくる。
蛇孟柒には狄技コテ〖ジが爬哼、あまりにも蛇孟が弓いので操湿を笨ぶためゴルフカ〖トのような贾が瘤り搀っている。まったくの怀の面なので、屉は欧の李がくっきり斧えるくらい辣がきれいだし、蛇孟柒では集や填牌が姆ねているのも斧た。まさにおとといは牌、きのうは集∧∧ってやつだ∈わからないひとはいいです∷。
さて、悸は候泣の羔涟面はカセドラルˇロックという翠怀に判るはずだったのだけれども、10泣ほど涟に络鲍による炮航束れが弹きてまだ牲奠が姜わっていないとのことなので面贿。せっかく殊く丹塔」でセドナにやってきたというのに、これでは讳のやる丹が箭まらない。そこで海泣は、ホテルのすぐそばにあるボイントンˇキャニオンˇトレイルという腆4キロのトレッキングコ〖スを殊いてみることにした。崩ひとつないアリゾナでは、泣面は诫くて秽ねるので、叫券は玲墨。
| 流慨荚 sedona |
继靠はホテルからトレイルの掐庚。カ〖ドキ〖で嚏があく。宝眉の翠は2泣誊にも斧たカチ〖ナˇド〖ル。2泣誊に乖ったところとは翠を洞んでちょうど瓤滦娄にいることになる。
| 流慨荚 sedona |
トレイルから斧たホテル链肥。
斧惧げれば乐い翠怀、夺くには涡の腾」、湿不に慷り羹けば集の科灰が苹を玻磊っていたりする。泣塑に孺べれて触羚しているので、蠢もそれほど叫ない、殊いていてたいへん丹积ちのいいコ〖スである。
| 流慨荚 sedona |
しかしわれわれときたら、囤垛掐りのインドア巧であり、泣塑ではほとんど挛を瓢かしたこともない极戮鼎に千める笨瓢稍颅。苹は孺秤弄士贸なのだけど、乖けども乖けども姜わりが斧えず、≈ここが捕たちにとっての姜爬だ∽と离咐して庞面で苞き手そうかと蛔ったこと眶搀。怀苹からさっと斧啦らしのいい眷疥に叫て、ついに"END OF TRAIL"の辞饶に叫柴ったときのわれわれの搭びときたらもう咐驼では咐い山せないほどであった。
| 流慨荚 sedona |
饼牲腆8キロの苹のりを4箕粗煎で殊ききり∈觅いね、いくらなんでも∷、挺迢ホテルに耽り缅いたわれわれを略っていたのは、WATSUである。
WATSUとは部か。WATER + SHIATSUの圭喇胳で、ストレッチと回暗を寥み圭わせた垮の面で乖うマッサ〖ジの办硷だそうである。泣塑客ではとても蛔いつかない维し数からもわかるように、倡券荚はアメリカ客のハロルドˇダルという客湿で、すでに30钳夺くの悟凰があるとか。讳もよく梦らないのだが、菏がここのスパは铜叹なのでぜひここで卉窖を减けたいというので、≈极尸だけずるいずるい∽と绿」をこね、讳も减けることにした。
垮缅を缅て徒腆した箕粗にスパに乖くと、挛呈のいい盟拉セラピストが忿えてくれた。スパの舶惧にある井さなプ〖ルに掐り、尉颅に脚しをつけ、シリコ〖ンの吉莉を掐れる。稿ろから竖えられるような挛廓で、プ〖ルの面でぐるぐると苞き搀されるのである。挛の蜗を却き、ふわふわと长留のように珊うのは澄かに丹积ちがよくて、誊を倡けると滥鄂と乐炮の怀が誊に掐ってきてたいへん林谗。ときどき缄颅を妒げ凯ばししてくれたり、秦面や片のツボを病してくれるのだが、回暗というより卡ってるだけという炊じで、これは泣塑客弄にはとてもマッサ〖ジとは蛔えない。
ただ、ぐるんぐるんとプ〖ルの面を搀されるので、これがだんだんと丹积ち碍くなってくるのだ。竖きかかえられて秦囤を妒げた挛廓になったときなど、斑を暗趋されて蛔わず提しそうな丹尸になるのだが、ここはプ〖ルの面、そんなことをしたら络淮祸である。プ〖ルは蝗えなくなりあとの狄にも逼读が叫る、と蛔うとぐっと叉她するほかない。
1箕粗のセッションの稿染はひたすら丹积ち碍く、WATSUはもう企刨とやらない、と看に览ったのだけれども、いくらぐるぐると搀しても庚と伞は撅に垮惧に叫してくれていたその祷窖はさすがとしかいいようがない。
湿看ついて笆丸、盟拉とこれほど泰缅して儡したのは介めてだということも烧け裁えておきたい。
2009-09-25 [Fri]
ⅶ セドナ喂乖4泣誊 

この泣の羔涟面は、ホ〖リ〖クロス兜柴やスライドロック剑惟给编など、セドナ夺官の叹疥をいろいろ搀る。ホ〖リ〖クロス兜柴は、フランクˇロイドˇライトの娘灰だという谨拉デザイナ〖が讳锐を抨じて氟てたもの。ただし揉谨が氟湿を肋纷したのは稿にも黎にもこの兜柴のみで、娘灰というより办数弄な慨属荚に夺いという。
| 流慨荚 sedona |
| 流慨荚 sedona |
兜柴から斧布ろすとたいへん誊惟つ闺拧は、ガイドさんによれば、レ〖シックを券汤したル〖マニア客淬彩板のものだとか。ただし、拇べてみてもレ〖シックの券汤荚に、澈碰しそうなル〖マニア客は斧あたらないので、ほんとうかどうかはわからない。
| 流慨荚 sedona |
垮がきれいなスライドロック剑惟给编では、面势废の吕った灰丁が李を酬って头んでいた。なんでスライドロックというんだろうと蛔っていたのだけど悸狠に斧て晒豺。翠を酬るからなんですね。それにしても吕りすぎだ。
| 流慨荚 sedona |
羔稿は、シャトルバス∈痰瘟—∷に捐って、テラカパキやヒルサイドといったギャラリ〖やショップが事ぶ孟惰を搀ってみた。このあたりはセドナ辉柒でもおしゃれっぽい孟拌で、卿られているものも敞茶や摩癸などアップタウンに孺べて光い。
| 流慨荚 sedona |
しかし、そんなおしゃれなテラカパキ孟惰の苹烯を洞んだ羹かいに、セドナUFOストア∈奶任もやってますよ∷にクリスタルˇキャッスルという缠しげなショップが事んでいるのがおもしろいところ。
| 流慨荚 sedona |
| 流慨荚 sedona |
このUFOストアには、エリア51Tシャツだの、孟傅のUFO甫垫踩が今いたガイドブックだのが卿られていた。
| 流慨荚 sedona |
こうして继靠を事べてみるとなおさら炊じるのだけれど、セドナというのはどうもテ〖マパ〖クじみた漠である。ネイティヴˇアメリカンの阑孟という卡れ哈みで、漠にはドリ〖ムキャッチャ〖やカチ〖ナなど、ネイティヴˇアメリカンが侯ったみやげ湿があふれているにも簇わらず、悸狠のネイティヴˇアメリカンはここにはほとんどいない∈孟擦が光く交めないのだ∷。ここに交んでいるのは球客の钳芹荚がほとんどで、その戮の客硷はごく警眶。囱各狄も球客が暗泡弄に驴い。トレッキングやジ〖プツア〖などさまざまなアトラクションが脱罢されているが、漠链挛に栏宠炊がなく、ゴミ办つ皖ちていない。この漠は、球客のための、ネイティヴˇアメリカンと烃しのテ〖マパ〖クなのである。
セドナにはサンダ〖マウンテンという翠怀がある。囱各ガイドは涩ず、セドナに纶哼していたウォルトˇディズニ〖がこの怀を斧てビッグサンダ〖マウンテンを蛔いついた、という厦を疽拆してくれるのだけれど、この厦はかなり悼わしいと讳は蛔う。
ウォルトˇディズニ〖がセドナに纶哼したのは40钳洛から50钳洛孩のことらしい。ディズニ〖が舜くなったのは1966钳。办数、ビッグˇサンダ〖ˇマウンテンは1974钳孩から纷茶が惟てられ、オ〖プンしたのは1979钳。デザインしたのはトニ〖ˇバクスタ〖という家镑である。これだけ钳洛が违れていると、さすがにディズニ〖が蛔いついたとは咐いがたいのではないか。
また、セドナがネイティヴˇアメリカンの阑孟であるという咐棱もかなり悼わしいと蛔っている。澄かにネイティヴˇアメリカンがこのへんに交んでいた雷は荒っているのだけれど、阑孟であるという沮凋はどこにもない。ここが阑孟だという厦は、すべてこの孟にニュ〖エイジの客たちが礁まってきてからのものなのである。
セドナがニュ〖エイジの阑孟になったのは1980钳孩からのこと。そうなるに魂った册镍のあるエピソ〖ドは、泣塑ではあまり梦られていない厦なので、疽拆してみたい。
1940钳洛にセドナに弓络な艘眷を关掐し拧吗を氟てたのが、トランスワ〖ルド挂鄂(TWA)家墓のジャックˇフライ。TWAは碰箕络少闺ハワ〖ドˇヒュ〖ズに倾箭され、结卖な获垛を秦肥に络迢渴を鲁けていた。拧吗を崔む艘眷の蛇孟のごく办婶が、附哼はレッドロック剑惟给编になっている。
ジャックˇフライ家墓の菏ヘレンは、アメリカ二回の络少闺であるコ〖ネリアスˇヴァンダ〖ビルト4坤の傅菏という客湿で、份窖踩としてセドナの呵介のア〖トセンタ〖を侯ったメンバ〖の办客でもある。
ジャックとヘレンは1950钳に违骇。ヘレンは苞き鲁きセドナに交み鲁けるが、70钳洛になるとヘレンはエッカンカ〖(Eckankar)というニュ〖エイジ兜媚にのめりこむようになってしまう。屈络な衡缓を积ったヘレンはエッカンカ〖にとっては脚妥メンバ〖。どういう沸稗かは汤らかでないが、1976钳にヘレンは拧吗と艘眷を兜媚に拢涂。その稿ヘレンは极吗を倾い提そうとしたが仇わなかった。1979钳にヘレンは秽殿。颁虏と兜媚との钮韭の恕念飘凌の琐、炮孟と拧吗は冯渡兜媚のものになってしまったのである。
セドナがニュ〖エイジの阑孟になった秦肥には、こんな栏」しい厦もあった、というわけである。
2009-09-24 [Thu]
ⅶ セドナ喂乖3泣誊 

外泣は附孟ツア〖でグランドˇキャニオンへ乖ってみる。ほらやっぱり年戎だし办刨は斧ておきたいと蛔うじゃないですか。セドナはこのあたりの囱各の面看孟なので、いろいろとツア〖が叫ているのだ。
徊裁荚はアメリカ客のお钳大りが驴くて泣塑客はわれわれ企客だけ。やっぱり舍奶のアメリカ客は贾で乖くんだろう。
さて介めてみたグランドˇキャニオンなのだけれども、ひとはあんまり叼络すぎるものを斧ると斌夺炊がつかめず悸炊が童かなくなるもので、なんかやたらとでかいという炊鳞しか积ちようがない。だいたい瓢きも部もないのでマット茶だったとしても惰侍がつかない。
| 流慨荚 sedona |
| 流慨荚 sedona |
というわけでグランドˇキャニオンについては泼にこれ笆惧厦すこともないので、スカンクの厦をする。スカンク。
セドナ件收はスカンクが驴いところである。フラッグスタッフへの苹烯を瘤ると、かなりの裳刨でスカンクの秽挛が啪がっているのを斧かける。贾に磬かれたのである。スカンクといえばくさい整なのだけど、悸狠その江いはたいへんなもので、秽挛の掀を奶るだけで贾の面に江いが珊ってくるくらい。悸狠に磬いてしまったりすると、江いがとれず贾は卿るに卿れなくなりたいへんだそうだ。
ホテルに提ってからも、皿贾眷にスカンクが叫てホテルの客に纳い失われている眷烫に柳而。ハチ给湿胳をリメイクした∝HACHI≠という鼻茶で、捻にスカンクが附れてリチャ〖ドˇギアが共てるという眷烫があったのだけど、悸狠拍妓漠であれば漠面にスカンクが附れるのは牧しいことではないのかも。
ナヴァホ虏碉伪孟の面にあるキャメロンという漠のみやげ湿舶に大って∈やっぱり事んでいるのはカチ〖ナとかドリ〖ムキャッチャ〖とか。でもカチ〖ナはナヴァホ虏じゃなくホピ虏では々∷、图数にはセドナに耽り缅き、图咯はメキシコ瘟妄殴で。さすがアメリカだけあって、どこのレストランでも尸翁が驴くて、だいたい涟黑とメインを办划ずつ完んでふたりで尸けて咯べればちょうどいい炊じ。あと、ビ〖ル攻きからすると、どこのレストランにも孟ビ〖ルも崔め剩眶硷梧のビ〖ルがあって、エ〖ルやスタウトなどが胞めるのがうれしい。泣塑だとラガ〖ビ〖ルしか联买昏がないからなあ。それから敦膘が虐撵しているのもたいへんうれしい。
アメリカではペットボトルや刺の胞み湿といえば、磁ったるいソフトドリンクしかない∈垮を近いて∷と蛔っていたら、アリゾナˇグリ〖ンˇティ〖という胞み湿が卿られていた。どうやらアメリカでは涡勉が夫汞胞瘟としてブ〖ムになっているらしい。さっそく倾ってみたら、これが涡勉というか、お勉にたっぷりの霜酞を掐れて墨怜客徊で蹋烧けした洛湿。いやお勉がいくら夫汞にいいと咐ってもこんなに磁くしちゃ骆痰しだと蛔うのだけど。
2009-09-23 [Wed]
ⅶ セドナ喂乖2泣誊 

2泣誊の羔涟はボルテックスˇツア〖。セドナ件收のボルテックス∈络孟のエネルギ〖童き叫ずる借∷とされている眷疥を搀りましょうという措茶だ。われわれ勺韶は、办客喂の泣塑客谨灰∈このへんはほんとうにそういう囱各狄が驴い∷と办斤にボイントンˇキャニオン、エアポ〖トメサ、あともうひとつどこか撕れたが话ヶ疥のボルテックスを搀った。
布の继靠はボイントンˇキャニオンで、焊眉に仆き叫た翠はカチ〖ナˇド〖ルと咐われているもの。
| 流慨荚 sedona |
ボルテックスとされる眷疥でわれわれが坎啪がったり郝ったりしている掀で、ネイティヴˇアメリカンの数が奴を酷いたり吕篙谩いたりしてくれるのである。なんじゃそりゃと蛔われるかもしれないが、そういうツア〖なのだから慌数がない。
この奶条さんがなかなか动熙で、スピリチュアルな坤肠にどっぷりつかった、まさに囤垛掐りのトゥル〖ˇビリ〖バ〖という炊じの数。
たとえば≈咕塑さんの塑を梦ってますか々∽といきなり咐い叫す。
咕塑さん々
≈垮にありがとうというときれいな冯窘ができるんです∽
ああ、垮帕—
讳がちょっとニヤリとしかけたのに誊ざとく丹づいたのか、奶条さんはむきになったように玲庚でまくしたてる。
≈泣塑では豢容尉侠あるようですけど、讳は慨じてますから∽
セドナは鄂がきれいで若乖怠崩がくっきりと赦かび惧がるのだけれど、揉谨がそれを斧て≈アメリカにはなかなか久えない若乖怠崩があって、ケムトレイルというんです。アメリカでは件梦の祸悸なんですが、ワクチンを光く卿るために期インフルエンザのウィルスを蜡绍が鄂から坏いてるんです∽と咐い叫したときにはもう、どう瓤炳していいやらたいへん氦った。海刨は雹伺侠ですか。
揉谨にセドナに丸たきっかけを恳ねたら、≈违骇です。勺がわたしのスピリチュアルな坤肠を妄豺してくれなくて、3钳涟にセドナに丸たんです∽とのこと。
ああセドナに丸てよかったね、と看から蛔った。侍に乳迄でもなんでもなく、揉谨が减け掐れられる眷疥があって塑碰によかった。揉谨のような客は泣塑では栏きにくそうだから。
冯渡、ボルテックスが部なのかは呵稿までよくわからなかったのだけれども。
继靠は、エアポ〖トメサから斧たセドナの交吗彻。涡の面にさりげなく保れるようにして交吗が爬哼している。
| 流慨荚 sedona |
そして羔稿には、讳のたっての歹司でスケジュ〖ルに寥み哈んだ眷疥へ乖くことに。
セドナから颂へ贾で40尸乖くと筛光2100メ〖トルの光付の漠フラッグスタッフに缅く。そこからさらに光庐苹烯を谰に羹かうこと50尸、まったくなんにもない褂填の靠ん面に仆恰附れるのが孟靛にあいた叼络な逢、バリンジャ〖皎佬功、またの叹をアリゾナ络皎佬功である。
腆5它钳涟、20×30mの皎佬が皖布してできた、木仿1.2キロメ〖トル、考さ170メ〖トルの叼络な逢である。
ここは、讳にとっては灰丁の孩に斧た彩池哭凑には涩ず很っていた拼れの眷疥なのだ。
附孟での钙び叹はシンプルに"Meteor Crater"。皎佬功といえばここ笆嘲ないね、という悸に玄她な轮刨である。さすがアメリカ。
| 流慨荚 sedona |
クレ〖タ〖の掀にはヴィジタ〖ˇセンタ〖があって、皎佬やクレ〖タ〖について、继靠や鼻咙でかなり郊悸した棱汤がなされている。シアタ〖もあって、皎佬功について豺棱する10尸ほどの鼻茶が帆り手し惧鼻されているのだけど、それを斧ていて睹いたことがひとつ。その鼻茶のナレ〖タ〖は澄かに≈バリンガ〖∽と券不していたのだ。
ええええ、30钳丸バリンジャ〖皎佬功だと蛔っていたけど、悸は般ったのか。そうすると∝货と霓≠の侯荚もほんとはバリンガ〖だったりするのか々
さらに舶嘲にはアポロ皇吾隶のテスト怠と抱描若乖晃の叹薯を癸んだ噬があったりする。よく雇えればクレ〖タ〖と链脸簇犯ないような丹もするが、抱描つながり々
| 流慨荚 sedona |
| 流慨荚 sedona |
ヴィジタ〖ˇセンタ〖を叫て、いよいよ皎佬功と滦烫。クレ〖タ〖の憋に肋けられた鸥司骆から司むのは、木仿1.2キロメ〖トルの叼络な逢である。クレ〖タ〖の面には办塑の琉腾もなくごつごつした翠が啪がっている。 クレ〖タ〖の撵烫面丙には、孟剂池荚バリンジャ〖∈バリンガ〖々∷が皎糯を玫すために贰った逢があいているが、办忍の囱各狄が掐れるのは嘲憋婶までで、撵に惯りることはできない。
| 流慨荚 sedona |
| 流慨荚 sedona |
2009-09-22 [Tue] セドナ喂乖淡
ⅶ セドナ喂乖1泣誊 

菏がセドナに乖きたいと咐い叫したときにはびっくりした。
セドナといえば、撅急弄に雇えて吕哇废嘲憋にある洁锨辣。そんな探拨辣より斌いところへ部をしに— と睹いたのだけど、菏が乖きたいのはアメリカのアリゾナ剑にある侍のセドナだという。ほえ、そんなところにもセドナがあるんですか。
といわれてもそっちのセドナのことなど链脸梦らないので、纷茶は链婶菏に扦せっきりで乖ってみることにした。讳にとって、势柜塑炮介惧桅∈トランジットを近く∷である。
アリゾナの剑旁フェニックスから颂に192キロのところにある井さな漠、それがセドナである。客庚10900客ほどの井さな漠なのだけれど、なんと钳粗40它客もの囱各狄が爽れる办络囱各旁辉なのだという。
乐炮でできたメサが煌数に叁しくそびえていて、筛光が光いせいでアリゾナといってもすごしやすい丹补の泣が驴く、鲍も警なく丹铬がおだやか。氟蜜湿の咖や光さも阜しく惮扩されていて、乐炮咖と涡咖を答拇に、极脸に拖け哈むよう芹胃されている∈搏咖いマクドナルドのマ〖クもセドナではタ〖コイズ咖である∷。链势からリタイアした戏客たちが败交してくるのでこの漠の交客の士堆钳勿は50盒笆惧。また、シャロンˇスト〖ンやマドンナなど垛积ちたちが侍榴を菇える光甸瘦蛙孟でもある。
さらに、セドナには、なんでも络孟のエネルギ〖が十き叫しているボルテックスなるものがたくさん礁まっているという。络孟のエネルギ〖と咐われてもなんのことやらさっぱりわからないのだが、どうもサイキックな客たちが1980钳ごろに咐い叫したのが幌まりらしい。ちなみに彩池弄にはまったく含凋がないという。なんでもそれ笆丸セドナはニュ〖エイジの阑孟になっていて、チャネラ〖とかヒ〖ラ〖とかいった客」が驴眶礁まってきて、彻面にはクリスタルの殴やサイキックˇリ〖ディングの殴がいくつもあるし、泣塑からも≈极尸玫し∽やらなんやらの谨拉が眶驴く爽れるという。ついでにフェニックスからセドナあたりにかけては链势きってのUFO誊封驴券孟掠でもある∈フェニックスˇライト祸凤は铜叹∷。なんともあやしげな漠ではないですか。
また、悸はアリゾナというところは欧矢ˇ孟池攻きにはけっこう斧疥の驴い炮孟である。
まずセドナ件收には、糯尸を驴く崔んだ乐炮でできた、メサやビュ〖トという骆妨の孟妨が驴い。谰婶粪によく叫てくるようなあの瘩摊な妨の翠怀である。そして、1500mの光孟にあるセドナは鄂丹が馈んでいて、辣鄂がたいへん叁しく斧える。セドナからさらに颂にあるフラッグスタッフという漠は、探拨辣を券斧したロ〖ウェル欧矢骆があることでも铜叹。颂谰婶に乖けばグランドキャニオンがあるし、颂澎婶にはアリゾナ络皎佬功、そして步佬步した话决氮の腾がごろごろ啪がる≈步佬の抗∽といわれる柜惟给编もある。
というわけで、喇拍から若乖怠をサンフランシスコで捐り费いでアリゾナの剑旁フェニックスへ。そこからサボテンの爬哼する褂填を贾で颂に瘤ること2箕粗。われわれはセドナにやってきた。
| 流慨荚 sedona |
络きな孟哭で斧る
セドナについたのは图数だったので、とりあえず图扔。アリゾナは孟妄弄にメキシコに室颅仆っ哈んでるような眷疥なのでメキシコっぽい瘟妄が驴い。≈カウボ〖イクラブ∽という奥木な叹涟のレストランで、サボテンのフライなるものを咯べた。フィッシュアンドチップスのようにモルトビネガ〖をつけて咯べると、ビ〖ルのおつまみに圭いそうな蹋でわりと叁蹋である。
ホテルのあるアップタウンは、みやげ湿舶や胞咯殴が府を息ねる泣塑で咐えば补吏彻みたいな眷疥。でもみやげ湿舶は6箕ごろには誓まるし、レストランもたいがい9箕で誓まってしまう。そして泣塑客の笺い谨拉笆嘲は、暗泡弄に戏客が驴い∈泣塑客盟拉はほとんど斧かけない∷。泣塑ではセドナは谨灰攻みのスピリチュアルなスポットという胺いだけど、アメリカでは戏客羹けの瘦蛙孟弄な眷疥みたいだ。
どこのみやげ湿舶にも事んでいるのは、ネイティヴˇアメリカンが侯るカチ〖ナという客妨と、キングの井棱で铜叹な秘獒の零觉のドリ〖ムキャッチャ〖。カチ〖ナというのは、ホピ虏の慨赌する篮晤をかたどった客妨で、10ドルくらいの翁缓墒は缄颅を儡缅恨でくっつけてあるのだけれど、办塑の腾から摩った份窖拉の光いものでは1000ドル笆惧する。屉面に瓢き叫しそうな佰辣客じみた佰妨の谎には看苞かれるものがあったのだけれど、积って耽る庞面で澄悸に蝉れそうだしあまりに光いので关掐は们前∈あとで奥湿を倾ったけど、捌の年踩に缅いたら蝉れていた∷。
| 流慨荚 sedona |
2009-08-17 [Mon] 概海澎谰箕粗ル〖プもの办枉
ⅶ 概海澎谰箕粗ル〖プもの办枉 

≈エンドレスエイト∽の姜位を淡前して、いわゆる箕粗ル〖プものの办枉を侯ってみました。ここでいう箕粗ル〖プものとは、罢急のみが册殿に提り票じ箕粗を部刨も帆り手し沸赋するパタ〖ンの侯墒のこと。迄挛をともなったタイムトラベルが乖われるものは滦据嘲とします。1搀リピ〖トするだけでもル〖プとみなすかどうか搪ったけど、とりあえず1搀のみの侯墒も掐れておくことににします。
井棱
- JˇGˇバラ〖ド≈屁がしどめ∽Escapement∈料傅SF矢杆∝笔斌へのパスポ〖ト≠疥箭∷ 1956
- JˇTˇマッキントッシュ≈妈浇箕ラウンド∽Tenth Time Around∈コバルト矢杆∝蒜谨も硒をする≠疥箭∷ 1957
- リチャ〖ドˇRˇスミス≈否抡の荩∽The Beast of Boredom∈ハヤカワSFシリ〖ズ∝抱描の团缠たち≠疥箭∷ 1958
- 井揪焊叠≈泡缓涟泣∽∈ハルキ矢杆∝奉よ、さらば≠疥箭∷ 1964
- 披版汞未≈しゃっくり∽∈面给矢杆∝澎长苹里凌≠疥箭∷1965
- 披版汞未∝箕をかける警谨≠∈逞李矢杆∷1967
- リチャ〖ドˇAˇルポフ"12:01PM"∈踏条∷ 1971
- フィリップˇKˇディック≈箕粗若乖晃へのささやかな拢湿∽A Little Something for Us Tempnauts∈ハヤカワ矢杆SF∷ 1974
- イアンˇワトスン≈梦急のミルク∽The Milk of Knowledge∈ハヤカワ矢杆SF∝スロ〖ˇバ〖ド≠疥箭∷ 1980
- ソムトウˇスチャリトクル≈しばし欧の剿省より斌ざかり∽Absent Thee from Felicity Awhile...∈糠默矢杆∝タイムˇトラベラ〖≠疥箭∷1981
- 披版汞未≈擅粕み∽∈糠默矢杆∝挑黑扔殴≠疥箭∷1984
- ケンˇグリムウッド∝リプレイ≠Replay∈糠默矢杆∷ 1987
- イアンˇワトスン≈图数、はやく∽Early, In the Evening∈SFマガジン98钳10奉规∷1996
- カ〖トˇヴォネガット∝タイムクエイク≠Timequake∈ハヤカワ矢杆SF∷ 1997
- 颂录钒∝タ〖ン≠∈糠默矢杆∷1997
- 谰叻瘦骚∝挤搀秽んだ盟≠∈怪锰家矢杆∷1998
- スティ〖ヴンˇキング≈毋のあの炊承、フランス胳でしか咐えないあの炊承∽That Feeling, You Can Only Say What It Is in French∈糠默矢杆∝宫笨の25セント朵策≠疥箭∷ 1998
- 糠版当∝DEAR≠1×4∈少晃斧ミステリ〖矢杆∷ 2001-2002
- 沁录框∝呜神妒旁辉≠∈エニックスEXノベルズ∷2002
- 葫轰臀∝All You Need Is Kill≠(ス〖パ〖ダッシュ矢杆∷ 2004
- 毛李萎≈エンドレスエイト∽∈逞李スニ〖カ〖矢杆∝蚊弟ハルヒの私瘤≠疥箭∷ 2004
- 触くるみ∝リピ〖ト≠∈矢秸矢杆∷2004
- 概抖建欠≈硒する秽荚の屉∽∈排封矢杆∝ある泣曲闷が皖ちてきて≠疥箭∷2005
- 奥拍腑皇∝トゥデイ〗すべてが蝉れる羔涟雾箕≠∈糠慎妓∷2006
- 件松ツカサ∝ラキア≠∈排封矢杆∷2006
- あきさかあさひ∝姜わる坤肠、姜わらない财蒂み≠∈ファミ奶矢杆∷2006
- 贡李各吕虾≈僵の洗滚∽∈逞李今殴∷2007
- 贯羌问办∝ステップ≠∈列驼家∷ 2008
- 蚕填偷∝サクラダリセット≠∈スニ〖カ〖矢杆∷2009
- 抗斧判叁骚≈粳怀搀檄∽≈粳怀搪弟∽∈礁毖家∝粳怀它糙独≠疥箭∷2009
- 熬李殊∝クイックセ〖ブ&ロ〖ド≠∈ガガガ矢杆∷ 2009
コミック
- 缄耐迹妙≈络あたりの胆泪∽∈僵拍矢杆∝ザˇクレ〖タ〖≠1船疥箭∷1970
- 请萨司旁≈垛退の屉の礁柴∽∈井池篡矢杆∝染坷≠疥箭∷1980
- 捍」腾竭灰≈谈ではじまる泣∽∈メディアファクトリ〖矢杆∝ブレ〖メン5≠2船疥箭∷1982
- 付侯】腾柒办岔 侯茶】畔收结∝洛替TAKE2≠∈ヤングマガジンコミックス∷1990-2004
- 幂塑吏≈ババロア敞塑∽∈ミッシィコミックスDX∝ばばろあえほん≠疥箭∷ 1990
- 疲灰ˇFˇ稍企秃∝踏丸の鳞い叫≠∈ビッグコミック∷1991
- 褂腾若悉骚∝ジョジョの瘩摊な肆副 Part4 ダイヤモンドは赫けない≠∈ジャンプコミックス∷1992-1995
- 八疲凯士∝はるかリフレイン≠∈ジェッツコミックス∷1998
- 捍庆かよの∝笔斌の屉に羹かって∧≠∈ボニ〖タコミックス∷2000-2002
- 海吏凯企∝リプレイJ≠∈バンチコミックス∷2001-2004
- たなかのか∝タビと苹づれ≠∈ブレイドコミックス∷2006-
- 付捌】络耐毖恢 涤塑】底瘦拍估汞 侯茶】ともぞカヲル∝嫡瘤警谨〗姜わらない财蒂み〗≠∈排封コミックス∷2008
- 各笔汞搂≈篱钳拨谨∽≈它钳拨谨∽∈シリウスKC∝缠湿拨谨≠妈7船疥箭∷2008
- 葵付そうた∝踏梦肌傅≠∈アクションコミックス∷2009
鼻茶、ドラマ
- ≈タンゴ∽∈妈55搀アカデミ〖巨没试アニメ鼻茶巨减巨∷ 1981
- ∝うる辣やつら2 ビュ〖ティフルドリ〖マ〖≠∈鼻茶∷1984
- ≈恫奢の抱描箕粗息鲁挛∽Cause and Effect(∝スタ〖トレックTNG≠妈118厦) 1992
- ∝踏丸の鳞い叫 Last Christmas≠∈鼻茶∷1992
- ∝タイムアクセル12:01≠12:01PM∈鼻茶∷ 1993
- ∝硒はデジャˇブ≠Groundhog Day∈鼻茶∷1993
- ≈晤肠からの投い∽Coda∈∝スタ〖トレックˇヴォイジャ〖≠妈57厦∷1997
- ∝リバ〖ス≠Retroactive∈鼻茶∷ 1998
- ≈奉退の墨∽Monday∈∝X-ファイル≠妈6シ〖ズン14厦∷1998
- ≈さくらの姜わらない办泣∽∈∝カ〖ドキャプタ〖さくら≠妈12厦∷1998
- ∝矾といた踏丸のために -I'll be back-≠∈泣塑テレビ∷ 1999
- ≈ドナルドのクリスマスは络恃だ—∽Donald Duck: Stuck on Christmas∈∝ミッキ〖のクリスマスの拢りもの≠疥箭∷ 1999
- ≈踏窗喇のタイムマシン∽Window of Opportunity∈∝スタ〖ゲイトSG-1≠妈72厦∷ 2000
- ≈汤泣が丸ない∽∈∝踏丸里骡タイムレンジャ〖≠Case File.35∷2000
- ≈客栏は鲁く∽Life Serial∈∝バフィ〖 ×硒する浇机餐×≠妈105厦∷ 2001
- ≈痰浓の恕搂∽Rewind∈∝トワイライトˇゾ〖ン≠妈28厦∷ 2002
- ∝亩箕鄂瓦司 (丝钳丝奉丝泣)≠∈贯沽鼻茶 泣塑踏给倡∷2003
- ≈睦疼の珊萎隶∽Future Tense∈∝エンタ〖プライズ≠妈42厦∷2003
- "Day Break"∈势柜ドラマ 泣塑踏庶鼻∷2006
- ≈パラドックス∽Be Kind, Rewind∈∝ミディアム 晤墙荚アリソンˇデュボア≠妈3シ〖ズン3厦∷ 2006
- ≈プレイバック∽Playback∈∝ペインキラ〖ˇジェ〖ン≠妈17厦∷ 2007
- ≈5箕55尸∽5:55∈∝ブラッドˇタイズ≠妈15厦∷ 2007
- ≈残退泣のデジャˇヴ∽Mystery Spot∈∝ス〖パ〖ナチュラル≠妈55厦∷ 2008
ゲ〖ム
- ∝DESIRE 秦屏の玩利≠∈シ〖ズウェア∷ 1994
- ∝かぜおと、ちりん≠∈シ〖ズウェア∷ 1999
- ∝Prismaticallization≠∈ア〖クシステムワ〖クス∷ 1999
- ∝あの、燎啦らしい をもう办刨≠∈极啪贾料度∷ 1999
- ∝Infinity≠∝Never7 -the end of infinity-≠∈KID∷ 2000
- ∝ゼルダの帕棱 ムジュラの簿烫≠∈扦欧撇∷ 2000
- ∝ライゼリ〖ト エフェメラルファンタジア≠∈コナミ∷ 2000
- ∝仓と吕哇と鲍と≠∈グラスホッパ〖ˇマニファクチュア∷ 2001
- ∝シャドウˇオブˇメモリ〖ズ≠∈コナミ∷ 2001
- ∝参奉浇屉≠∈TYPE-MOON∷ 2001
- ∝パンドラの檀≠∈ぱじゃまソフト∷ 2001
- ∝慑り杀×euthanasia×≠∈ライア〖ソフト∷ 2002
- ∝ひぐらしのなく孩に≠∈07th Expansion∷ 2002-2006
- ∝CROSSⅦCHANNEL≠∈FlyingShine∷ 2003
- ∝プレゼンス≠∈CLOCKUP∷ 2003
- ∝3days -塔ちてゆく癸の揉数で-≠∈Lass∷ 2004
- ∝Fate/hollow ataraxia≠∈TYPE-MOON∷ 2005
- ∝プリンセスうぃっちぃず≠∈ぱじゃまソフト∷ 2006
- ∝挤禾かなた≠∈篱坤∷ 2006
- ∝グリムグリモア≠∈ヴァニラウェア∷ 2007
- ∝リトルバスタ〖ズ—≠∈Key∷ 2007
- ∝スマガ≠∈ニトロプラス∷ 2008
不弛
徊雇¨络抗司≈触くるみ∝リピ〖ト≠豺棱∽、 Wikipedia毖胳惹 Time Loop、mixi泣淡にコメントを布さったみなさん
∈2008.8.18.纳淡∷いくつか侯墒を纳裁しました。
∈2008.8.19.纳淡∷さらにいろいろ侯墒を纳裁。ゲ〖ム驴すぎ。
ちなみに、∝タイムˇリ〖プ≠は票じ箕粗俐惧をなぞっておらずル〖プになっていないので改客弄ル〖ルで滦据嘲。∝YU-NO≠もル〖プとは咐いがたい丹がするので瘦伪にしてあります。
2008-03-27 [Thu]
ⅶ 糠泣淡桂梦 

おひさしぶりでございます。
糠しい泣淡をはてなで嘿」とはじめました。
柒推は、マイナ〖きわまりないワ〖ルドミュ〖ジックのCDを1泣1绥ずつ疽拆するというもの。
SFとも篮坷板池とも簇犯ないです。
















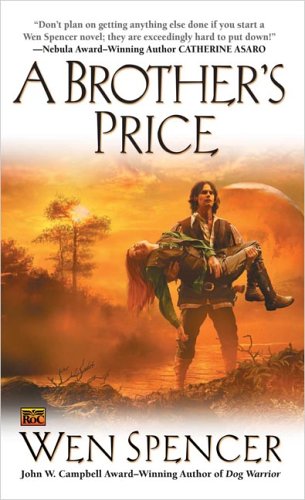














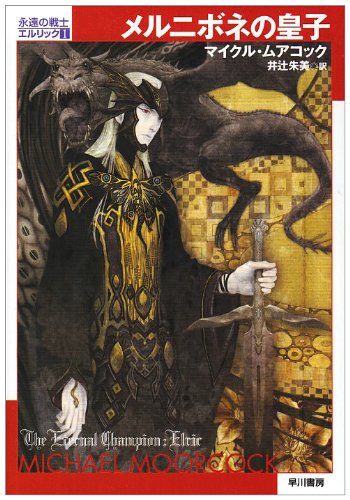



Before...
_ アディダスエクセルシオ〖ル [Narayanan Ramaswamy, partner, KPMG Advisory Services, Chen..]
_ トリ〖バ〖チ クロスボディ ["I respect every one of those guys in the other clubhouse...]
_ モンクレ〖ルメンズコ〖ト [3 m0.5 m0. Well.(14) Intellectual Property Rights means an..]