精神病院と都市伝説――黄色い救急車をめぐって
小学生の頃のことだ。私たちの学校ではこんな話が広まっていた。
「頭のおかしい人のところには黄色い救急車がやってきて、精神病院に連れて行かれる」
誰が言い出したかはわからないし、実際に見たことがある人も誰もいなかった。それでも、当時の私たちにとっては、「黄色い救急車」は噂や物語ではなく、すでに常識に近かった。
今考えればなんとも差別的な話なのだが、ちょっとおかしなことをした友だちに「黄色い車が来るぞ」「イエロー・ピーポーが来るぞ」などとはやしたてるようなことは日常的に行われていた。私は一九六九年生まれだから、だいたい一九七〇年代半ば頃のはずだ。
同じ頃学校で話題になっていた「口裂け女」の話が、怪談めいた噂としてマスコミでも脚光を浴びていたのに対し、「黄色い救急車」は大きな話題になることもなかったが、まるで水のように自然なものとして、私たちのあいだに静かに広まっていた。
その後成長するにつれ、私は「黄色い救急車」のことなどすっかり忘れてしまった。それを、しばらくぶりに思い出したのは、ちょうど「人面犬」「消えるヒッチハイカー」などの都市伝説がブームになっていた頃のことだ。そういえば、あの頃は噂とは思っていなかったけれど、考えてみれば黄色い救急車など一度も見たことがない。もしかしたら、あれも実は都市伝説のひとつだったんじゃないか。そう思っていくつかの本を読んでみたが、不思議なことに、「黄色い救急車」の話はどこにも見つからなかった。
ひょっとしたら、こんな噂が流行したのは私たちの小学校だけだったのかもしれない。そう思って周囲の友人に訊いてみると、多くの人がその話を知っていることがわかった。しかも、思いがけないことに、黄色い救急車は知らないが、緑の救急車なら知っている、という人もいたし、中には紫色の車なら知っている、という人までいたのである。どうやらこの噂、見かけによらず奥が深そうだ。
さらに何年かのち、晴れて精神科医となった私は、精神病院には黄色い救急車などというものはなく、患者が搬送されてくるときも、やってくるのはごく普通の白い救急車だということを知った。それでは、いったい「黄色い救急車」の噂はどこから来たのだろうか。
がぜん興味を抱いた私は、一九九八年一二月、個人で開設しているホームページ上に、「黄色い救急車」に関するアンケートを設置してみた。それから一年半近く、ありがたいことに全国各地から四〇〇人以上の方が回答を寄せてくださった。それによってわかったのは、どうやら色の分布にはある程度の地域性があり、噂の内容にはバリエーションがあるということ。
本稿では、とりあえず現在までの調査の範囲内での結論と考察を記しておきたい。
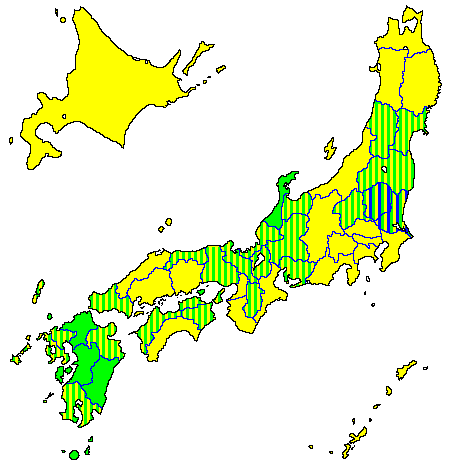 県ごとの回答の分布は別ページの表を参照していただきたい。そして、日本地図を救急車の色別に塗り分けたものが右の図である(インターネット人口は大都市に集中しているため、このアンケートでも県によっては極端に回答者数が少なくなってしまっている。ネットを使った調査は簡便ではあるが、地域、年齢などにかなりの偏りが出てしまう点が欠点といえるだろう)。
県ごとの回答の分布は別ページの表を参照していただきたい。そして、日本地図を救急車の色別に塗り分けたものが右の図である(インターネット人口は大都市に集中しているため、このアンケートでも県によっては極端に回答者数が少なくなってしまっている。ネットを使った調査は簡便ではあるが、地域、年齢などにかなりの偏りが出てしまう点が欠点といえるだろう)。
回答者数が少ない県もあるため、この結果だけで地域性を語るのはまだ尚早かもしれないが、救急車の色の分布にはかなりはっきりとした地域性があることがわかる。おおよそ、(1)南東北〜北関東、(2)京都を中心にしてその東側の富山、静岡あたりにかけての地域、それから(3)山口〜九州一帯に「緑色の救急車」地域があるようだ。その他の地域はほとんどが黄色で、全国的にみれば黄色が優勢といえる。
緑色が優勢な三地域の共通項は、正直なところ不明である。別に柳田國男の方言周圏論もあてはまらないようだし、これといった原因も思い当たらない。この点の解明は今後の課題である。
また、とくに興味深いのが茨城で、黄色でも緑でもなく「青い救急車」の噂が伝わっている地域があるらしい。茨城は、南東北の「緑」と南関東の「黄色」がせめぎあっている上、独自の「青」が加わり三色が混沌としている。あるいは、この近辺に、病院車として青い車を使用していた精神病院が実在するのかもしれない。
さらに、宮城県と群馬県に「紫」という回答があったほか、統計にはあらわれていないが、「紫の話も誰かから聞いたことがあるような気がする」(福島県)、「(黄色の話が広まっていたが)でも本当は紫なんだよ、と言われていた」(東京都)などのコメントも寄せられている。紫色の報告は今のところ東日本のみである。
次に、色の由来についての回答をみてみると、「黄色はキチガイのキだから」という単純な理解が大半を占めており、たしかに私自身も子どもの頃にはこの説明で納得していたような記憶がある。「アメリカでは州立精神病院に患者を収容するときに黄色い救急車を用いるから」というまことしやかな理由づけもあったが、たとえ事実だとしても、それがこの噂の由来とは思えない。また、緑色、青色、紫色の由来についてははっきりした説明を記した回答は寄せられなかった。
「黄色い救急車」「緑の救急車」のほか、「イエロー・ピーポー」「グリーン・ピーポー」という呼び名もかなり広く普及していたようだ。「ピーポー」は救急車のサイレンの音だとする回答が一般的だが、中には「イエローピ−ポーはyellow peopleのことで、どこからともなく救急車が現れて、黄色い服を着せて連れて行く。このせいで、黄色い服を着ていると『イエローピーポー、イエローピーポー』とはやされていました」(埼玉県)といったコメントもあった。
次に、この言葉が使われた状況についてのコメントを紹介しよう。
「小学生時代に、子ども達がはやし言葉として使ってました。『おまえアタマおかしいんちゃうんか! 黄色い救急車がくるぞ〜!』ってな感じで」(滋賀県)
「小学生の頃、人の悪口など言うときに、『あいつ頭おかしいんじゃないか?』 『うん、そのうち緑の車がお迎えにくるよ』などという会話が頻繁になされていて、その緑の車は都立××病院から来ることになっていました」(東京都)
「私の場合は、小学生の頃クラス内で『キ○○イは黄色い救急車で××病院に連れていかれるで〜』とみんなに混じってはしゃいでいたことを思い出します」(兵庫県)
以上のようなコメントからもわかるとおり、怪談や伝説というより、主として子どもたちの間のはやし言葉として流布していたところが多い。
また、親が子どものしつけの中で言いきかせることもあったようだ。
「子どもの頃、夜更かしをしていると、よく親に『早く寝ないとピーポーが来るよ』と言われていた」(山口県)
「小さい頃、よく『そんなきちがいみたいなこといってると、黄色い救急車につれていかれるよ』と父親に言われた」(静岡県)
さらに、「中学校の国語の授業中、騒いでいる人がいて、その人に向かって先生が『イエローピーポーを呼ぶ』と言っていた」(埼玉県)
「小学生の頃、ちょっと変な、行動・言動をすると教師に『××に緑の救急車で連れて行かれるぞ』と言われた」(愛知県)
など、先生から聞いたという人も少なくない。
このように、噂を知った経路としては、おおむね友達、親、教師の三パターンに分かれる。まあ、子どもが日常的に接する人間といえば、だいたいその三種類なので、これは当然の結果だろう。
また、近くに古くからある精神病院がある地域では、たいがい噂はその病院と結びつけられているようだ。アンケートの中でも、黄色、あるいは緑色の救急車で実在の精神病院へ連れて行かれる、というコメントが多く寄せられた。
そのほか付随する噂として、「通報者にはお金がもらえる」という話も広く流布していた。金額はなぜか三千円か五千円。この噂も、青森県から大分県まで全国各地から寄せられた。
救急車からは離れるが、精神病院のことを「赤い屋根」と呼んでいた、という回答も、少数ながら北海道、秋田、神奈川とさまざまな地域から寄せられている。
さらに現実離れした噂になると、「黄色い救急車に乗って紫色の病院に連れて行かれる」(静岡県)、「緑の病院に連れて行かれる」(徳島県)といったものもある。中には「母が昔『精神病院の奥には壁一面真っ赤な部屋があって、普通の人をここに入れて、おかしくする』と言っていました」(埼玉県)、「精神病院から逃げてきた患者は 黒い白衣(黒衣?)の医者に連れていかれるという話は親から聞きました」(北海道)などというコメントも。まるでメン・イン・ブラックである。どうやら、人々のイメージの中の精神病院は、エキセントリックで恐怖に満ちた場所のようだ。
また、かなり遅くまで本当のことだと思っていた人も多いようで、実際、このアンケートで知るまで事実と信じていたという人もかなり多かった。「このサイトでそのような救急車がないことを知り、とても驚きました」「グリーンピーポーがただのデマというのはショックでした。この歳まで本気で信じてました」などのコメントが次々と寄せられたのにはこちらが驚いたくらいである。
以上が、私の調査した「黄色い救急車」伝説の概要である。同じような噂が全国に流布しており、少しずつバリエーションが加わっていることがわかる。
では、このような噂はいつごろ、どうして全国に広まったのだろうか。
ひとつ考えられるのは、実際に精神病院で黄色、もしくは緑色の車が使われていた可能性である。
「私の家のすぐ近くに精神病院があり、その前で実物の黄色い檻付きの救急車(実物は白の救急車とは異なり、ライトバンでした)から拘束衣を着せられて運ばれている人を見たことがあります」(愛知県)
「近くの総合病院の名前が書いてある緑色の乗用車(ライトバン)を見たことがあるので、救急車ではなく事務職や往診のときに病院の名前入りの車が使用されていたのではないでしょうか? 精神科の名前入りの車で訪問されていたらそういう噂になるように思います」(東京都)
といった回答もあり、こうした車の存在が噂の元になっているのかもしれない(しかし、いくらなんでも「紫」は実在しないと思うが)。
噂のバリエーションとして、救急車の車体全体が黄色もしくは緑色というのではなく、救急車自体は白色だが十字マークや回転灯が黄色か緑だと言われていた、というコメントも全国から寄せられている。こちらは、車体が黄色というよりは現実的であり、そうしたデザインの病院専用車が実在した可能性は十分考えられる。
また、噂の元ではないかと複数の方から指摘があったのが、一九六二年公開の『危(やば)いことなら銭になる』(中平康監督)という映画である。この映画の中で、宍戸錠演じる主人公は、ライバルを出しぬくため、黄色い宣伝カーから「こちらは東京精神病院です。先ほど狂暴な患者が病院から脱走しました。この人物の特徴は……。付近の皆様は十分注意してください」などと嘘の放送を流すのである。指摘してくださった方によれば、この映画が上映された一九六二年頃を境に「黄色い救急車」伝説が広まった記憶がある、とのことである。
 私もつい最近この映画を観る機会があったのだが、個人的にはこの映画が噂の元であるとは思えなかった。映画に登場するのは黄色い救急車ではなく「日清チキンラーメン」と書かれた辛子色のバンであり、患者を車に乗せるという場面もない。また、このシーンは映画の中では本筋とはあまり関係のない短い挿話にすぎず、この映画から「黄色い救急車」の話が広まったと考えるのは無理があるように思われる。
私もつい最近この映画を観る機会があったのだが、個人的にはこの映画が噂の元であるとは思えなかった。映画に登場するのは黄色い救急車ではなく「日清チキンラーメン」と書かれた辛子色のバンであり、患者を車に乗せるという場面もない。また、このシーンは映画の中では本筋とはあまり関係のない短い挿話にすぎず、この映画から「黄色い救急車」の話が広まったと考えるのは無理があるように思われる。
さて、この映画とちょうど同じ時期、雑誌『精神衛生』の一九六三年六月三一日号(ママ)には、「精神病はどう考えられているか」という座談会が掲載されている。この中で、司会の笠松章が「冗談などで、何か突飛な話をすると、東京では『松沢行き』、京都では『岩倉行きだ』といいます」といった発言をしており、やはりこうした噂は一九六二年ごろ(座談会が行われたのは一九六二年一一月一二日)からあったことがわかる。ただし、残念ながらこの対談では「黄色い救急車」への言及は見られない。
そこで、また別の方面からこの伝説の由来について考えてみたい。「戦前から伝えられている」「親の世代から存在する」などという回答もあったが、黄色い救急車の伝説が存在するためには、まず救急車自体が存在しなければならないはずだ。では、そもそも今のような救急車ができたのはいつごろなのか。消防大学校編著『救急実務』(ぎょうせい)によれば、日本初の救急業務が行われたのは、一九三一年一〇月、日本赤十字社大阪支部でのことらしい。最初の救急車は民間のものだったのである。初めて救急車が配置された消防機関は横浜市中区山下消防署。一九三三年のことである。戦前には、消防機関に救急車があったのは横浜、名古屋、東京、京都、金沢、和歌山の六市のみなので、戦前から「黄色い救急車」の伝説が広まっていたとはどうも考えにくい。
救急業務が法制化されたのは時代をはるかに下って一九六三年のこと。一一九にかければ救急車が呼べるようになったのはこの年からということになる。それまでは各市町村や赤十字、病院などが独自に救急業務を行っていたらしく、なかには霊柩車を救急車代わりにしていた地方もあるという(病院に搬送した患者が亡くなった場合、帰りは本来の目的で使用するわけである)。法制化されたあとも救急車はなかなか普及せず、地方によっては昭和四七年ごろにもまだ霊柩車が使われているところもあったとか。
つまり、全国的に救急車が普及したのは一九六〇年代頃ということになる。
以上のように、アンケートの回答や救急車の普及などの手がかりなどから考えて、この噂が全国に広まったのは一九六〇年代と考えていいと思われる。それでは、一九六〇年代というのは精神医療にとってどんな時代だったのだろうか。
ひとことでいって、一九六〇年代の日本の精神医療はきわめて低レベルであった。劣悪といってもいい。
一九六〇年代には、精神科病床は年間一万五〇〇〇床から二万床近くも急増していったが、これは営利目的の民間精神病院が激増したためで、精神科医一人あたりの病床数は増加、平均在院日数は上昇、といった具合に治療の質はむしろ落ちていった。一九六一年には精神衛生法が一部改正され、措置入院の国庫負担率が一〇分の八に引き上げられたことにより、一九六四年末には措置患者比率が三七・五%に達する(一九九七年の措置患者比率は一・四%である)。
精神障害者は社会から排除され、大量につくられた民間精神病院に隔離収容された。岡田靖雄によれば「一九六一年はわが国の精神病院が収容所化の方向へさらに歩をすすめた転換の年」であった。一九六〇年代の精神病院は、治療の場ではなく収容施設だったのである。
さらに一九六四年になると、アメリカのライシャワー駐日大使が一九歳の分裂病患者に刺されるという事件が起きる。日本政府はただちにアメリカ政府に陳謝するとともに、当時の国家公安委員長が「高度の政治的責任」をとらされて辞職。翌年には、保安的色彩を強めるかたちで精神衛生法が改正されている。
しかし、その後の六〇年代後半から七〇年代になると、世界的な大学紛争、反精神医学の波に乗って、精神医療のさまざまな矛盾が明るみに出ることになる。看護人の暴力や、ロボトミー批判などの記事が次々と新聞や週刊誌を飾り、一九七〇年には朝日新聞の大熊記者が精神病院に潜入して『ルポ・精神病棟』を連載、さらに精神医療のあり方を問う裁判もいくつか行われている。一九六〇年代後半は、収容所的な精神医療に批判が集まり、精神医療へのマイナスイメージが、マスコミを通じて広まった時代といえるだろう(このマイナスイメージは、現在まで尾を引いている)。
「黄色い救急車」は、まさにそんな時代を背景に流布していった伝説なのである。「黄色い救急車」の噂にも、そうした社会全体の精神医学へのマイナスイメージが色濃く反映していることは間違いないことだろう。
アンケートで寄せられたコメントの中には、こんなものがあった。
「自分たちが子どもの頃聞いた話。頭のおかしくなった人のところに家族の通報で緑の救急車が急行。中から屈強な男達が現れておかしな人を連れ去っていくらしいと言っていた。最近まで本当だと思ってました」。
これを読んだとき私は驚いた。「本当だと思っていた」どころではない。これはまぎれもない事実なのである。
精神医療関係者以外にはあまり知られていないことだが、入院を拒否する患者を自宅から病院まで連れていく公的な制度(「移送制度」と呼ばれている)は、つい最近まで日本にはまったくなかった。「自傷他害のおそれ」がある場合は措置入院という手段が使えるが、そうでない場合は、あくまで患者の家族の責任で病院まで連れて行くしかない。
しかし、家族の責任と言われても、両親が高齢で患者が暴れている場合など、連れてくるのがとても無理なことも多いだろう。
こうした場合どうするかというと、医師が患者宅へ往診に行き、患者を取り押さえて鎮静剤を打って眠らせ、車に乗せて病院まで搬送、即入院させてしまう。法に触れるかどうか微妙なところだが、つい最近まで行っていた病院もあるし、一九六〇年代ならば多くの病院で行われている日常風景だったはずだ。
ただし最近では、法的な問題を恐れ、家族から相談を受けた場合にも往診などせず、移送サービスを行っている警備会社の電話番号を教える、という対応を取っている病院が多い。この場合、患者を押さえつけるのは警備会社の職員であり、警備会社の車で病院まで連れていくことになる。
つまり、警備会社に依頼したのはあくまで家族の責任であって、病院側が無理矢理連れてきたのではない、という理屈なのだが、これはいかにも苦しげな論理だし、いくら保護者の要請とはいえ警備会社の職員が患者を拉致するのはどう考えても違法だろう。
それに、往診にせよ警備会社にせよ、病院側の責任という点では大きく違うのかもしれないが、入院させられる患者にとっては大した違いはない。どちらにせよ、無理矢理押さえつけられて得体の知れない場所に連れて行かれるというだけのことだ。
ここでもう一度先に紹介したコメントを思い出してみよう。「家族の通報で」ある日突然車がやってきて、「中から屈強な男達が現れておかしな人を連れ去っていく」。これは、「緑の救急車」という部分をのぞけば、今述べた実際の入院風景のきわめて正確な描写ではないか。
考えてみれば、「黄色い救急車」の伝説というのは、「黄色」「緑色」というエキセントリックな色の部分こそ現実的ではないものの、少なくとも「精神障害者のところには、どこからか普通の救急車ではない車がやってきて、閉鎖された病院に連れて行ってしまう」という部分はまぎれもなく真実なのである。しかも、一九六〇年代の精神病院は、まさに都市伝説さながらの恐ろしい収容施設だった。ということは、私たちは、子どもながらに噂をささやきながら、実はかなり真実に近いところを語っていたのである。
平成一二年四月、改正精神保健福祉法が施行され、長年の間規定がなかった移送制度について初めて明確に規定されることになった。しかし、法律が施行されたとはいえ、この移送制度については今のところまだ運用体制がきちんと整っていないのが現状である。移送制度が実際に動き出すまでには、もう少し時間がかかりそうだ。
「黄色い救急車」について調べるにあたり、都市伝説や怪談の本をいくつか読んでみたのだが、そのうちに私は奇妙なことに気づいた。病院というのは怪談の人気スポットである。病院にまつわる話はいくつもあるし、中には「病院もの」だけを集めた本さえいくつか出ている。しかし、そういった本にも、「黄色い救急車」はおろか、精神病院にまつわる物語は一つも収録されていないのだ。
もちろん、ひとつの理由は、差別問題にかかわる微妙なテーマだからあえて収録を避けた、というものだろう。しかし、それ以前に、そもそも精神病院というのは都市伝説の題材にはなりにくいのではないだろうか。
都市伝説や怪談というものは、学校(とくにトイレ、実験室など)、トンネルなどのように、異界と日常世界との接点を好んで舞台にする。病院もまたそんな舞台の一つだ。しかし、一般の人にとっての精神病院は、接点どころではなくすでに異界である。そして、おそらく日常世界との接点を持たない異界そのものは、怪談の舞台にはならないのだ。
だから、精神病院の場合、普通の病院のようにその内部が舞台になるのではなく、内部と日常世界とをつなぐ救急車を題材にした噂が流布したのだろう(「口裂け女は実は精神病院から脱走して来た」というように、精神病院が都市伝説の題材として使われることはあるが、これも異界内部が舞台になっているわけではない)。
一般の人は、病院の中で何が行われているか知るよしもないし、そもそも精神病が一般の目から遠ざけられている現状では、精神病がどんなものなのかも知らない人が多いだろう。未知のものに対して恐れと畏れを感じるのは当然のことだ。
映画やドラマなどには精神病院内部が出てくることがあるが、その描かれ方はまさに異界そのものであることが多い。たとえば、最近の日本映画(『39』、『CURE』、『なぞの転校生』など)の中で描かれる精神病院は、どれも閉鎖的で非人間的な、まるで社会の不条理性そのものの象徴のような場所である。精神科医にとってはなんとも現実味を欠いているように感じられるのだが、たぶん、それが一般の人の感じるリアリティというものなのだろう。
そして、精神病院という異界に患者を運ぶ救急車が平凡な白でいいはずがない、という心理もまた、そう考えれば自然なもののように思える。黄色、緑、紫といったエキセントリックな色の救急車は、一般の人から見た精神病院の異界性の象徴といえるのかもしれない。
さらにいえば、こうした精神病院への異界イメージは、最近の精神病院がらみの事件――たとえばバスジャック事件の少年を一時帰宅させたこと――へのマスコミや一般の反応とも、どこかで通底しているような気がする。
以上が「黄色い救急車」をめぐる私の推理である。「黄色い救急車」の噂が語り継がれてきた背景には、一九六〇年代の収容所的な精神医療、今なおあいまいなままの移送制度の問題、そして精神病院に対する異界イメージ、といった要素が複雑にからみあっている……のではないだろうか(直接的な証拠が何もないのが痛いところだが)。「黄色い救急車」は噂ではあるけれど、噂が流布するにはそれなりの理由があったのである。
精神科医は、一般の人の持つ精神病や精神病院のイメージを、えてして無知による偏見として片付けがちである。精神病院を異界ととらえるイメージは偏見であり、偏見はなくすべきだ。そして偏見をなくすためには、精神科の実態をもっと一般に知ってもらう必要がある。確かにそれは正論なのだが、一方で、そうした見方はちょっと一面的すぎるような気もする。
偏見だからなくすべきだ、といった価値判断からはいったん離れ、そうしたイメージが長い間人々の心の中に根を張っていて、今なお噂として息づいているということ。その事実を静かに見つめ、理解する視点もまた、必要なのではないだろうか。

県ごとの回答の分布は別ページの表を参照していただきたい。そして、日本地図を救急車の色別に塗り分けたものが右の図である(インターネット人口は大都市に集中しているため、このアンケートでも県によっては極端に回答者数が少なくなってしまっている。ネットを使った調査は簡便ではあるが、地域、年齢などにかなりの偏りが出てしまう点が欠点といえるだろう)。
私もつい最近この映画を観る機会があったのだが、個人的にはこの映画が噂の元であるとは思えなかった。映画に登場するのは黄色い救急車ではなく「日清チキンラーメン」と書かれた辛子色のバンであり、患者を車に乗せるという場面もない。また、このシーンは映画の中では本筋とはあまり関係のない短い挿話にすぎず、この映画から「黄色い救急車」の話が広まったと考えるのは無理があるように思われる。
